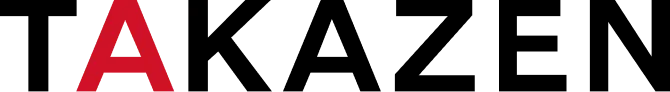COLUMN
成人式振袖・卒業式袴選びのお役立ちコラム
コラム2022/07/29
振袖を着るときに必要なものリスト一覧|各アイテムの特徴と役割を紹介

着物はたくさんの小物を用いて着付けをします。特に振袖の際は、通常の着物以上にたくさんのアイテムが必要になります。振袖を着る当日になって慌てることのないように、事前にリストを確認しておくと安心です。今回は、着付けに必要なものとその役割を一覧でご紹介します。
振袖時に必要なアイテムのチェックリスト一覧
振袖の着付けに最低限必要なものをチェックリストにまとめました。事前にチェックして、着付けの当日に慌てないよう準備しておきましょう。
- ● 振袖
- ● 半襟
- ● 重ね襟(伊達襟)
- ● 襟芯
- ● 振袖用の帯
- ● 帯揚げ
- ● 帯締め
- ● 帯枕
- ● 腰紐
- ● コーリンベルト
- ● 伊達締め
- ● 三重紐または四重紐
- ● 補正用タオル、パッド
- ● 肌襦袢
- ● 長襦袢
- ● 足袋
- ● 髪飾り
- ● ショール
- ● 草履
- ● バッグ
振袖
「振袖」は未婚女性の第一礼装で、袖が長いことが特徴です。振袖の袂(たもと)の長さは3種類あり、一番長い「大振袖」は約3尺(約114cm)もあります。成人式でよく使用されるのは「中振袖」で、長さは約2尺9寸(約110cm)です。そして「小振袖」はより短くなり、基準の長さは約2尺(約75cm)となっています。
襟まわり
着物の襟にあたる部分のアイテムです。見える面積は小さいですが、襟は顔のすぐ近くのパーツなので色や柄が顔映りにも影響します。
半襟
肌に一番近い襟を「半襟」といいます。半襟は、振袖の下に着る長襦袢に取り付けて汗や皮脂汚れを防ぎます。オーソドックスな半襟は真っ白の絹製で、古風で清楚な印象を与えられます。晴れの日の成人式には、華やかさを演出できる柄物や刺繍、絞り加工などの半襟がおすすめです。
重ね襟(伊達襟)
振袖の襟元を見ると、着物を何枚も着ているように見えます。これは、襟部分のみ「重ね襟」を合わせてボリュームを出しているためです。「伊達襟」とも呼ばれ、振袖姿を豪華に見せる役割を果たします。
襟芯
「襟芯」とは、長襦袢の襟の部分に差し込んで使うものです。襟芯という名の通り、着物の襟に芯が通ったようにハリを持たせるために用います。プラスチック素材で作られているのが一般的ですが、なかには襟元のムレを防ぐメッシュ素材のものもあります。
帯まわり
帯まわりには、振袖用の帯だけでなく振袖姿を華やかにする装飾アイテムや、帯をきれいに着付けるための道具などが必要になります。
振袖用の帯
振袖をはじめとしたフォーマルな着物には「袋帯」という帯を使用します。カジュアルな場面でよく使用される名古屋帯や浴衣などで使う半幅帯は、振袖には使用しないので注意しましょう。袋帯は長さが約4メートルあり、名古屋帯よりも長いのが特徴です。これにより、凝った変わり結びができます。
帯揚げ
「帯揚げ」は帯の上辺につける飾りのアイテムで、帯の背中側の飾りを支える「帯枕」を包んで隠す役割を持ちます。絞りやちりめんなどの素材がオーソドックスですが、近年の振袖コーディネートではレースやフリルといった洋風テイストのものもよく使用されます。
帯締め
帯の中央で締める紐状のアイテムを「帯締め」といいます。幅1cmほどの平たいタイプや、丸いタイプ、花飾りなどのアクセントがついたタイプなど、バリエーションはさまざまです。
帯留め
「帯留め」は、和装用のブローチのようなもので、帯締めに通して使用します。振袖用の帯締めは華やかなものが多いため、かつては振袖に帯留めを使用しないのが主流でした。しかし、成人式の振袖スタイルとして多様な着こなしをするようになった現在は、こだわりのポイントとして帯留めを合わせることも珍しくありません。
帯枕
「帯枕」は帯の結び目の中に仕込んで使用します。帯の土台として形を整えたり、飾り結びをボリュームアップさせたりする役割を持ちます。
帯板
帯の間に差し込んで、帯にハリを出す道具を「帯板」といいます。振袖のときは帯を飾り結びにすることが多いため、帯板を使って土台を安定させる必要があります。帯のお腹側に使用するものを「前板」、背中側に使うものを「後ろ板」といいます。
着付け用小物
ここまでご紹介したアイテムの他にも、振袖をきれいに着付けるための小物はいくつかあります。
腰紐
「腰紐」は、長襦袢や振袖がはだけないように結ぶための布製の紐のことです。その他に、身体に合わせて長襦袢や振袖の長さを調整するためにも使います。一般的には5〜6本使用しますが、着付け方によって本数が変わるので、多めに用意しておくと安心です。
コーリンベルト
二重になったゴム紐の両端にクリップがついているものを「コーリンベルト」と呼びます。着物の襟元をクリップで挟んで着崩れを防ぐために使います。1〜2本用意しておきましょう。
伊達締め
「伊達締め」は、腰紐の上から巻いて着崩れを防ぐアイテムです。「マジックベルト」と呼ばれることもあります。絹製、化繊、ゴム製のものがあります。
三重紐または四重紐
3枚の平ゴムが重なったものを「三重紐」、4枚重なったものを「四重紐」といいます。帯の変わり結びをするときに、重なったゴムの間に帯を挟んで形を作ります。
補正用タオル、パッド
着物の着付けは、身体の凹凸をなくして寸胴にするほうがきれいに仕上がります。補正用タオルやパッドは身体つきによって必要な枚数が異なるので、多めに用意しておくと安心です。
下着

振袖の下には和装用の下着を着用します。快適さだけでなく仕上がりにも影響するため、慎重に選びましょう。
肌襦袢
肌に直接身につけるアイテムを「肌襦袢」と呼びます。上肌着と裾よけのツーピースのものや、上下一体のワンピースなどがあります。普段使いしているスリップや肌着でも代用はできますが、胸元やうなじ、袖口など、外から見えない形のものを選ぶ必要があります。
長襦袢
肌襦袢の上には薄い着物状の「長襦袢」を身につけます。長襦袢は、振袖の袖の丈にあったサイズを選ぶのがポイントです。長すぎると袖の下のほうでふくらんでしまい、短すぎると振袖の袖口からはみ出してしまうなど、美しく振袖を着ることができません。事前にサイズを確認しておきましょう。
和装用ストッキング
振袖は、成人式や卒業式といった寒い季節に着ることが多いものです。必須ではありませんが、「和装用ストッキング」を用意しておくと寒さ対策になります。膝下から足首までをストッキングで覆ってゴム紐を足裏にかけるタイプや、つま先が二股に分かれて足袋が履きやすいようになっているタイプなどがあります。
足袋
振袖のときの「足袋」は白い絹製が定番です。後ろの留め具が4枚ついている足袋なら足首をしっかり包んでくれるので、振袖の裾から肌が見えにくくなります。履きやすさを優先するなら、ストレッチ性のある化繊のものや、留め具のない靴下のようなタイプでも良いでしょう。
足袋はサイズが合っていないと足が痛くなるので、当日までに履いてみてサイズの確認をしておくと安心です。
ファッションアイテム

華やかな仕上がりにするためにも、下記のファッションアイテムを忘れずに揃えましょう。
髪飾り
古風なかんざしタイプや、洋風のコサージュタイプなど、髪飾りの種類は豊富にあります。顔まわりを飾るアイテムなので、振袖との相性はもちろん、自分の顔や髪型に似合うかどうかもチェックしてください。
ショール
寒い季節に振袖を着る場合、首元の防寒対策としてショール選びも重要になります。毛足の長いファーや、洋装にも使えるカシミア、ベルベットなどの素材があります。写真を撮るときにも目に入るアイテムなので、こだわって選んでみてください。
草履
振袖用の草履は、金糸や銀糸、エナメルなど、華やかな素材を使ったものが定番です。近年の振袖コーディネートは自由度が高まっているので、ぽっくりのようなかかとの高いものや、ブーツを合わせる着こなし方もあります。
バッグ
バッグは草履とセットになっているものを選ぶと色や柄が揃い、コーディネートの統一感がアップします。バッグは長く使用できるアイテムなので、購入するなら他の着物や洋装にも合わせやすいシンプルなデザインがおすすめです。
まとめ
振袖を着るときに必要なアイテムはたくさんあり、表から見えない部分の細かな小物についても色々と準備しなければなりません。振袖&袴レンタルショップ・スタジオのTAKAZENでは、振袖の着付けに必要な30点ものアイテムをフルセットでレンタルできます。
下着や足袋など、一般的に自分で用意する必要があるアイテムまで揃っているため、自分で準備する手間が省けます。ぜひ、チェックしてみてください。
人気の記事
- 成人式・卒業式の振袖・袴レンタルなら【TAKAZEN】トップ
- お役立ちコラム
- 振袖を着るときに必要なものリスト一覧|各アイテムの特徴と役割を紹介